監修:S・マーフィ重松(東京大学助教授) 監修・翻訳:岩壁 茂(お茶の水女子大学助教授)
■VHS ■日本語字幕スーパー ■収録時間:46分 ■解説書付
■商品コード:VA-2005 ■¥48,600(税込) |
|
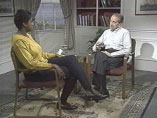 |
ラスキン博士は、長年に渡りカール・ロジャースと共同研究に取り組み、これまで世界数十カ国において来談者中心療法の理念を忠実に引き継ぐ「人物中心学習訓練」を行なってきた。来談者中心療法の実践において、クライエントの体験の「意味」を理解し、自己発見・自己探究を援助することが強調されるのが本セッションによって明確に示されている。クライエントは、今まで知らなかった自己の側面と対面し、「自分はこんな人間になってしまうのか」という不安に苛まれた。そして、家族に対する様々な思いの中で葛藤し、身動きがとれなくなる。ラスキン博士は、共感的理解によって、クライエントの複雑に絡んだ気持ちの糸を一つ一つときほぐしていく。クライエントは、理解されるごとに、見え隠れする「自分の姿」を発見し、自分の進み道を決めていく。そこには、クライエントが自分を探すのを支え、クライエントの感じること、クライエントの考えること全てを受け止めるロジャースの姿勢の基本が忠実に実践されている。
ナサニエル・J・ラスキン博士
(ノースウエスタン大学医学校名誉教授)
|
ナサニエル・J・ラスキン博士について
ナサニエル・J・ラスキン博士は1921年ニューヨーク市に生まれた。1941年にはオハイオ州立大学から修士号、1949年にシカゴ大学から博士号を取得した。オハイオ、シカゴのいずれの地でもカール・ロジャースと共に研究活動に従事した。現在、ラスキンはノースウェスタン大学医学部の精神科及び行動科学科の名誉教授であり、34年に渡り、臨床心理学研究科で教育と研究に携わっている。1980年以来、人物中心学習プログラム(Person-Centered
Learning
Program)をイタリア、フランス、英国、スロバキア、ハンガリーで指導し、ローマ、アムステルダム、コルク、モスクワ、セント・ペテルスブルグなどの都市より招かれ講演活動を行ってきた。また、1950年にはじめた個人開業を、現在でも継続している。博士は臨床心理学の認定資格をもち、APA理事、CCNYの名誉心理学系卒業生、さらに1978−80年の間には、アメリカ心理療法士学会(American
Academy of Psychotherapists)の会長も務めた。
クライエント中心療法の概要
クライエント中心療法のセラピストとして、ラスキン博士は以下のような態度が(時には、言葉で説明することによって)クライエントに伝わるよう努めている。「あなたの立場から、あなたの問題、気持ち、希望や恐怖、自分自身や他者へのあなたなりの見方、そうした点を私が理解しようとする関係を築くことによって、私は最大限にあなたの役立つことができると信じています。セラピーを進める中であなたのことを私が把握できなかったときは、私の誤解を修正してください。あなたとこのように関わっていく中で、セラピーに訪れる動機となった問題とその解決方法を明確にするのを助け、自分自身を十分に知り、さらに自分のなりたい姿に近づけるようになることを私は願っています。私は自分のことをあなたの問題点を指摘するような旧来の専門家ではなく、むしろあなたの自己探求の友である、と考えます。私は、あなたが自分自身、他者、世界をどのように見てどのように感じるのか、自分自身の価値観や決断を尊重する本当の自分になることを助けます。あなたの考えが私の考えと異なっていても出来る限りあなたの世界の理解に努めます。面接で扱うことは、あなたが話したいことに従い、あなたのやり方で探索し、面接の頻度や終了する時期もあなたの判断にお任せします。」
クライエント中心療法は、それまでの指導的介入や解釈を基礎とするアプローチとは異なる新たな選択肢として、1940年カール・ロジャースにより紹介された。ロジャースは、オハイオ大学とシカゴ大学の学生とともに、面接過程と結果をはじめて系統的、かつ包括的に研究した。彼は録音した面接のやりとりを分析することによって、セラピストが受容と尊重の態度を基礎として、一貫してクライエントの準拠枠を共感的に理解することに対する反応としてクライエントの自己発見と自己実現が一定のパターンに従い展開されることを確認した。そしてこの心理的風土を3つの「必要十分条件」、つまり共感、自己一致、無条件の肯定的関心と定義した。この定式化は数多くの研究を刺激し、セラピストが与える条件とセラピーの好結果の関係が正の相関関係にあるのを示すのに十分な実証的基盤を得た。ここでいう好結果とは、クライエント中心療法による自己への気づきの拡大、自己評価の高まり、価値観や基準の判断における自己に対する信頼の増大、より解放され、自発的で、開かれた自己世界体験の様式と定義される。
このビデオは、クライエント中心療法の特徴であるクライエントを中心とする一貫した共感表明が例解されている。クライエントが重要なポイントを自ら提示し、解決できる、とセラピストは信じ、注意深くシンシア(クライエント)の知覚、意味するところ、感覚の変化を聞き取ってゆき、単に「ええ」と頷くことや、より明確に言葉で反応することで彼自身の理解を伝えてゆく。言葉で表されることはないが、セラピストの理解が失敗に終わるとき、クライエントがその誤解を修正しやすい雰囲気が作り出されている。シンシアはこのアプローチの介入に対して好反応を見せ、セラピストの質問や指示を必要とせず、自らの問題の探求を自発的に進める。その結果、祖父母との縁がなかったことがシンシアには子供時代のつらい経験だったことや、母親や父親と一緒にいた頃のことを思い出せないことなど、新たな問題点が表出する。彼女はこうした話を感情を表に出しながら語ると、セラピストはその感情を肯定し、際立たせる。彼女は、家族のことを語るにつれて気づきが高まり、思いやりの感情を見せる。彼女の父親は、彼女と同様に不安な子供時代を過ごしたのだろうか。なぜ母親は支配的な性格になったのか。シンシア自身が母親と同じような道をたどっているのではないか。両親はお互いのどこに惹かれたんだろうか。家に子供達がいなくなった今、両親は仲良くやっているのだろうか。弟や妹たちは、多難な子供時代をどう過ごしてきたのか。シンシアは、自分がかつて年長で役割をもたされた子供だったことが、大人になった現在の異性関係における振る舞いにどのような影響を与えたのかなど、人生の様々な体験のあいだの関係を理解した。さらに彼女は一人の人間としての自分の強さに気付く。おそらく彼女は父親にもっと積極的にアプローチできたかもしれない。母親からの非難に甘んじているよりは、母に対抗できたかもしれない。やがてパートナーのケンの好きな部分と嫌いな部分もわかってくる。そして彼女はいくつかの結論に達する。「他者をコントロールするような人・親にはなりたくない。」「将来、自分の子供には愛情に満ちた環境下で育って欲しい。」「父・母それぞれが持つ強さを自分自身の強さにしてゆきたい。」
シンシアは2、3回質問をするが、セラピストはそれに対してすぐに応えず、質問が生じた背景にあるシンシアの態度や感情をセラピスト自身がどう理解するかを表明する。彼女は、理解されると探索を続け、面接の舵を取る。最終的に、クライエント中心の風土において、彼女は自らの過去・現在・未来を見渡し、その結果、問題把握・明確な理解・意思決定の過程を経験したのである。
クライエントの素性
■シンシア
■年齢:30歳
■性別:女性
■人種:アフリカ系アメリカ人
■婚姻関係:独身
■職業:保険会社外交員
■教育歴:学士終了
■両親:母(49歳);父(50歳);結婚31年目
■兄弟姉妹:弟一人、妹一人
関連する出来事
先週末、シンシアのボーイフレンドのケンが、野球中継を見るため数人の友人をアパートに招いた。試合後、ケンとその友人達は政治について話していたが、彼女はその議論には加わらず、ただ話を聞いているか、時折一言付け加えるだけだった。ある時点で、彼女から見ると「まるで的外れ」なことをケンが言い出したので、彼女は彼に対して意義を唱えた。それでも、ケンは自分の意見を変えず主張し続けたため、彼女はさらに彼に意義のコメントを加えた。すると、ケンは声を荒げて「うるさい!このバカが、自分が何言ってるのかわかってるのか!」と叫んだのだった。彼女はその場を離れベッドルームに逃げこんだ。
彼女傷つき、怒りを感じていたが、友人達が帰るまでは口を閉ざしていた方がいいと考えた。たぶん彼の言うことは正しいのだろう、と彼女は思ったが、たとえそうだとしても、彼への怒りは収まらなかった。友人達が帰ったら、ケンとしっかり話ができるだろう、そう思っていた。
友人達が帰った後、シンシアはケンと話をするためリビングルームに戻った。なぜ人前で自分を辱めたのかと彼に尋ねたかったのだが、彼女が言葉を発するより先に、人前で自分に恥をかかせた、とケンは怒鳴りシンシアを攻め立てた。このケンの態度に怒った彼女は手に持っていたグラスを壁に投げつけ、グラスは粉々に砕けた。するとケンはシンシアの顔に張り手を入れ、「何をしだすかわからんヤツだ」「ついにおかしくなった」などと彼女を責めた。怒り心頭に達した彼女は彼に向かって突進し、彼をたたいた。ケンは彼女の身体を持ち上げ、そしてなぎ倒した。
痛みと怒り、そして嘆きの中でシンシアは考えた、「いったい私のどこが悪いの?私のせいだっていうの?彼が正しいの?誰かに助けを求めないと。」
この出来事を振り返る中で、シンシアは以前にも同じような境遇に自分がいたことを思い出した。過去のボーイフレンドのうち2・3人は彼女に対し暴力的だったのである。その一人で見た目は子犬のように可愛いけれど、怒ると彼女にバカやろうと怒鳴る男のことを思い出した。もう一人には実際に身体的暴力を振るわれたことがある。彼女は数回も殴られたが、その男とは結局2年間も一緒に暮らした。こうした経験をするたびに、自分が悪かったのかと迷いながら、その男のもとを去った。彼女は自問した、「なぜ私はこんな男たちにはまってしまうのだろう。なぜ私はこういう経験を引き起こすのだろう。全て私が悪いのだろうか。」
これまでの面接の経緯
過去2回の面接では、クライエントが自ら率先して自分の問題についての話を進めた。まずラスキン博士を訪れるキッカケになった出来事について彼女の視点から語り、次に博士が彼女を理解できるよう、家族的背景の話もした。博士は共感的に彼女に反応してゆくことで、彼女が自分なりの方法で問題把握を展開できるよう共感的に反応した。
|